 �@
�@ �@�@�@
�@�@�@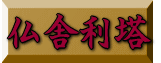
�����E���{�ɂ����Ă��ɗ����{�͌×����琷��ŗ쌱�k�������`����Ă���B
���Ƃ́H�@�i�����ł����A��E���ł��j
�@����
�@���{
�@�@���d��
�@�@�@�،o�̑���
�@�@����
CarIram
����͐g���B�ٖ��͑ʓs�i���ƁjdhAtu
���̈�g�B�܂��A���r�ɂ��Ă������i���{��Y���p����u�z�g�P����v�݂����ȁH�j
�㐢�A�u���ɗ��v�Ƃ������̂͑����͗���ŁA����߂čd���A������B
| �����F | ���ɗ� |
| �ԐF | ���ɗ� |
| ���F | ���ɗ� |
��L�E�́w�@����сx�̉��
| �S�g�ɗ� | ����@���̎ɗ��i�Ԍ���苗��̎ɗ����j |
| �Ӑg�ɗ� | �߉ޔ@���̎ɗ� |
| ���g�̎ɗ� | ������u���ɗ��v |
| �@�g�ɗ��i�@�ɗ��j | ��̑召��̌o���ɗ��� |
���̎ɗ��́A����d�̌O�K�ɂ���Đ�����̂ŁA��������{��q����Ό���������ƐM�����A
�×�����ɂ�������{��q����@����c�݁A�u�ɗ���v�u�ɗ��u�v�ȂǂƏ̂����B
����R�̏�y��ł́A�l���u���̎l���Ɏɗ��u���s���܂��B
�܂��A�ɗ����ɔ@�ӕ��Ɗς��ďC�����@����B
������A��̌o�T���ɗ�����^�����A���ׂĎɗ��Ȃ�ł���I
��X���ތ��Ȃ�C�����ŏ��ʂ��邱�Ƃɂ���āA
�ɗ���V���ɐ��ݏo������ł��I
�^�ʖڂɞ����̗��K���悤�Ǝv������A���@�[�́I�I
���܂��炾���B
| ���ɗ� �i�@���⍂�m�̓��̂̈ꕔ�j |
�Ӑg�ɗ� �i䶔��ɕt������Ɏc��j |
���ɗ��i�����F�j | ����������ʓI�Ɂu���ɗ��v���Ǝv���Ă�����́B |
| ���ɗ��i�ԐF�j | |||
| ���ɗ��i���F�j | |||
| �S�g�ɗ� | ��F�Ԍ���苗� | ���������āu���g���v���ăR���̈��H | |
| �@�ɗ� �i��̑召��̌o���ɗ���Ȃǁj |
�F���V�c�̂��́B�ؑ��S�����Ɏ��߂āu�ɗ����v�Ə̂����B |
���̃y�[�W�g�b�v���@�@�����߂����@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
![]()
�����ς̌�A���g��䶔��ɕt���A���̎ɗ��������o�������������B
���𗧂ĂĊe�����{�����B
�ɗ�����悤�}�c�����Ɍ������Ƃ���A�u���t�͉�X�̂Ƃ���ŖS���Ȃ����v�ƒf��A�����ɂȂ����B
�i���`�`�`�`�`���A�Ȃ�ł���A��Ȃ���ˁB
�u�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u��������v�u�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�@�E�E�E�E�E���Ă̂��ߑ��̋����������ł��傤�ɁI�I�j
�h�[�i�o�������i�R�[�������j���u��X�͎ߑ��̋������̂ł���v�ƌ����A��������邱�ƂɂȂ����B
�P�D�}�K�_�����@�A�W���[�^�T�g���i��苐��j��
�Q�D���F�[�T�[���[�̃��b�`�����B��
�R�D�߉ޑ��i�J�s�����@�b�c�j
�S�D�A�b���J�b�p�̃u����
�T�D���[�}���̃R�[������
�U�D���F�[�_���̂���o������
�V�D�p�[�����@�[�̃}�c����
�W�D�N�V�i�[���[�̃}�c����
�ԊO�B�h�[�i�o�������i�⍜�̓����Ă����ق����炢���{�j
�s�b�p�����̃��[�������i���z�̎c��̊D�����炢���{�����j
����ɂ͎��̂悤�ɎO�������ƁB
�P�D���V
�Q�D����
�R�D�l��
�P�W�X�W�N�A�C�M���X���݊��̃y�b�y�̓J�s�����@�b�c����P�R�������ꂽ�s�v�����[�ŌÕ��@�B
�߉ޑ��̎��߂����ɗ��ł��邱�Ƃ������A�܂��ߑ��̐^���B
����܂ʼn��Đl�ɂƂ��āA�ߑ��͎��݂̐l���ł���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B
�i�u�L���X�g�̂悤�Ɂv�Ƌ����������Ă����Ȃ��H�@�@���Đl���ăL���X�g�͗��j��̐l���ł͂Ȃ��̂��H�j
����̓^�C�����ɑ����A���̈ꕔ�����{�̖��É��̊o�����ɂ���B�s���ׂ��I
������ی삵���A�V���[�J���́A���ݎl��̓������A���{�̔�������ɗ����Ď��߂��B
�ȗ��B
�C����������A���̂����Љ�邩���B
�u�b�_�̎ɗ��̂ق��ɂ��A����̎ɗ��⍂�m�̎ɗ�������A
���݂ł��L���̑m��䶔��ɕt���Ǝɗ����c�邱�Ƃ�����炵���B
��X���u�̂Ǖ��v�ƌĂ�ł���͍̂b���͓�Ȃ�ŁA�Ռ`���Ȃ��R���s���܂��B
�Α���Ɏc��A�������T���Ă���p�̍��́A���ۂ͑��z�łł��B
���̃y�[�W�g�b�v���@�@�����߂����@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
![]()
�u���ɗ��i���g�̎ɗ��j�v�����u���邽�߂Ɍ��Ă��������A�@�ɗ��i���@�̘��u�j�����߂����̂��@�ɗ����ƌĂԁB
�V���N�ԂɍF���V�c�̔���ɂ��ؑ��S�ݓ��������B�����ɑɗ����i���E�ŌÂ̈�������������j�����߂Ă���B
�ɗ����ɂ͕`�E�@�،`�E���`�E��r�`�Ȃǂ������āA�����܂��͖ؑ��ɋ������\���Ă�����̂������A
�����ɂ͐����̕r�������Ă����Ɏɗ����[�߂��Ă���B
�����H�|�̋ɒn�ō���Ɏw�肳��Ă�����̂�����A���@�[�̃C�`�I�V�̓R���i�ޗǍ��������j�B
|
|
|
�����̑�d�����ɂ́u�ɗ����v�����u���Ă���B
��d���얀�d���ƁA�ɗ������J�p�b�ƊO���ƌ얀�F������܂��B
���̃y�[�W�g�b�v���@�@�����߂����@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
![]()
���Ƃ��Ɓu���v�Ƃ�stUpa�i�X�g�D�[�p�j�A�u�i�ߑ��́j�⍜��[�߂����v�̂��Ƃł������킯�ŁA
���łɍۂ��č��ꂽ�̂��N���ł��B
���߂͓y�\���̂悤�ȒP���Ȃ��̂ł����B
�������A�L�`�̕����́u�}��i���Ă��j�vcaitya�i�`���C�g���j�ƌ����܂��B
caitya�ɂ́A
�@ stUpa�i�⍜��[�߂����j
�A gaha�i������[�߂����j
�B kUta�i�⍜�Ƒ�����[�߂����j
�Ƃ����敪�����邻���ł��B�i�ɗ��̂Ȃ������`���C�g���ƌĂԐ�������j
���ꂪ�e�n�łǂ̂悤�ɓW�J���Ă��������A������ƌ��Ă݂܂��傤�B
����A�W�A�̓��́A��r�I�Â��l�����c���Ă��܂����A���A�W�A�̓��Ƃ͂܂���������������ɐi�����Ă��܂��B
�L���ȃV���G�_�S���p�S�_�����߁A�L���L���L����������A�Ƃɂ����h��ŃV���[�v�ȃV���G�b�g�B

�V���G�_�S���p�S�_
��������{�ƌ���I�ɈႤ�̂́A�u�ɗ���[�߂��e���v�ł͂Ȃ��A�u�߉ނ����v���Ƃ������ƂŁA
�p�S�_�̒��ł͗����ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ŃG���x�[�^�[�E�E�E�E�E���߂Ă̑̌��ł����E�E�E�E�E�B
���Ă��A�u�����͗����ŁI�v���Ă��������������B
�~�����}�[�̃p�K���ɉJ���⡂̂悤�Ƀj���L�j���L�ƃp�S�_�i�u�p�S�_�v�Ƃ����̂̓~�����}�[��ł͂Ȃ��p��j���������Ă���͈̂����ŁA�܂��܂��y���ɖ��܂��Ă��邻���ł��i3000���ȏ゠�邻���ȁj�B
����̔��@���y���݂ł��ˁB
���݂ɐ��E�O�啧����Ղɂ́A�p�K���̑��ɃJ���{�W�A�̃A���R�[�����b�g�A�C���h�l�V�A�̃{���u�h�D�[��������܂��i�����͈Ⴄ�̂ˁE�E�E�E�E�j�B
�t�������Ă����ƁA�A���R�[�����b�g�ƃ{���u�h�D�[���͑��̈�ՁB

�A���R�[�����b�g

�{���u�h�D�[��
���Ƀ{���u�h�D�[���͙�䶗��̐��E�ς𗧑̓I�Ɍ��킵�Ă��邪�A��䶗���ɕ���������ł���̂��ʔ����B
�����ɂ��鍂�w�̌����u�O�t�v�ƃ~�b�N�X����āA�C���h�Ƃ͂܂�����������i���𐋂��Ă����܂��B
�����o�T�́u�ܕ�������O�t�v�Ȃ��A�����ł͂����������ɔF�������킯�ˁ`�A�Ƃق�����ł��܂��B
�������A���̂悤�ɑ��`�͑傫���ω����Ă��܂������̂́A�u�ɗ���[�߂��e���v�ł���Ƃ������{�I�ȓ_�͓��P���Ă���B
����A�ł��A�悭����ƍו������Ē����ɃC���h�l�����Č����Ă����ł���i�����l�̔��ӎ��Ƃ����t�B���^�[�͂������Ă����ł����ǂˁj

�ؖ����u�_�����\�v�����č��J���ꂽ����ł���@�厛�^�g�B

�����̎��ŗL���ȉ��ߘO�B��̓��C�g�A�b�v����Ē��h�h��炵���B
���ꂼ�A���I�I
���N��������ѓ��{�ł́A���R�̂��ƂȂ��璆���̗l����`���Ă���̂ł����A���N�̂��Ƃ͂悭�m��Ȃ��̂œ��{�̂��Ƃɍi��܂��B
���{�̉����ɂ�����u���v�ɂ͂������̃p�^�[��������܂����A
���ʂ��Č�����̂́A�����̂��̂Ƃ͈���ē�����o��Ȃ��i��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��Ȃ��j���Ƃł��傤���B
�u�O�d���v��u�d���v���L���ł����A��d�`�\�O�d�̓��܂ł��邻���ł��B
���A���Ⴀ�d���͌܊K���Ăŏ\�O�d�̓���13�K���Ă��Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��A���������̂悤�ɂ����Ă��邾���ŁA
���t�͈����ł����u�Ȃ���ĘO�t�v�Ȃ�ł��ˁB
����������K�܂ŏ��邩�ȁ`���Č������̂������i������K�i����Ȃ��n�V�S���n���Ă��邾���Ƃ��j�A
�v����ɃV���{���I�Ȃ��̂ł��B
�i����R�̍��{�哃�������B��K�ɓ���Ȃ����Ƃ͂Ȃ��炵�����ǎQ�w����悤�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��j
�ŋߐV�������Ă�ꂽ�悤�Ȃ��̂́A�W�]������˂Ď��ۂɏ�����̂����邯��ǂˁB
���݂ɁA��ԌÂ��ؑ��d���͖@�����i���Ă��ؑ����E�ŌÁj�A��ԑ傫���d���͓����ł��I

���c�R�O�d��
���̑��ɁA�u���v�ƌ�����`���̂��̂�����܂��B
�u���v�Ɓu�v�͌����ɂ͈Ⴄ���̂��ƌ����Ă��܂��B
���������u�v�́u���v�̔��́A�܂�u���v�������Ɩ��C�Ȃ���Łu��v�Ƃ����`�e���������킯�ł��B
�u�X�`�����[�f�X�v�ł̓p�b�Ƃ��Ȃ��̂ŁA�u���l�X�`�����[�f�X�v�Ə̂���悤�Ȃ��̂ł��E�E�E�E�E������ƈႤ���H
����ɑ��āu���v�́w�@�،o�x���i��\��ɏo�Ă�����̂ŁA
�u�ߑ����@�،o����@���Ă���Ƒ�������A���ɂ���������������@�����������āA�ߑ��ɍ����������v
�Ƃ����G�s�\�[�h�ɗR������̂ł����A
���ۂɁw�@�،o�x���ɑ��̋�̓I�ȋL�q�͏o�Ă��Ȃ��̂ŁA�{���̂Ƃ���̑��̌`�͕s���ł��B
�������A���̏́i���T�ł́u�i�v�̓`���v�^�[�A�܂�u�́v�̈Ӗ��j�͂ƂĂ��h���}�`�b�N�ŗL���ȕ����Ȃ̂ŊG��̃e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B
�֑��ł����A�^���@��p�o�T�ɂ́w�@�،o�x�����25�͂ɂ����鑭�́u�ω��o�v�������Ă��܂����A���i�͂���܂���B
����ǂ��A���̃X�g�[���[�̏Ă������Ƃ�������ɗ���u��⟈�ɗ���v�������Ă��āA����͖����ǂނ��炢�|�s�����[�ł��B
���āA�v����ɁA�ߑ��Ƒ���@���̓������Ă��铃���u���v�ł��B
���́A�~�����}�[�ň꓃�̒��ɓ������Ă���p�S�_��q�ς�����������܂����A�W������̂��Ȃ��̂��s���ł��i�Ȃ��Ǝv�����ǁj�B
���āA�@�،o�̑����ǂ�Ȃ��̂ł��邩�͕s���ł��̂ŁA���ɍs���܂��B
���ۂɌ��z���ꂽ���̂����A����ɂ����āu���v�Ə̂�����̂́A���d�ʕ��`�A��d�ʉ~�`�Ƃ����w���ł��B
�����ł́A��������`�́u���v�ƒv���܂��B
���̌`���̓��́A���{�Ǝ��̂��̂��ƌ����Ă��܂��B
����ɋ��`�ɂ͏��d�����O�ԁi��ӂɒ����l�{�������Ԃ��O�Ԃ���̈Ӂj�̂��̂��u���v�Ə̂��A���܊Ԃ̂��̂���Ɂu�哃�v�Ə̂��܂��B
����Ă����̂́A���ɉ�炪�O�@��t�ŁA����R�̍��{�哃���\���Ȃ�ł��B
��t�̐��O�i�Ƃ���������O�j�ɂ͊������Ȃ�������ł����ǁB
���̖����Ǝ��̑��́w�@�،o�x�Ƃ͑S�R�W�Ȃ��A�u��V�̓S���v��͂������̂ł��B
�u��V�̓S���v�Ƃ́A�u��V�v�܂��C���h�ɂ������Ƃ����`���̓S���ŁA
����@�����疧����`����ꂽ�����T�b�^�͋��������̓S���ɔ[�߂Ă�����ł��ˁA
����𗳎��i�����ł́u���ҁF��イ�݂傤�v�ƌĂԁj���J���ē`�������E�E�E�E�E
��������l�ԊE�ɗ��`����̂ł�����A�����ɂ����Ă͂ƂĂ��d�v�ȃ��m�Ȃ�ł��B
�m���A���ݓ��{�l�����@���Ă���ƕ��������ǁE�E�E�E�E�B
��ԌÂ��ؑ����͐ΎR�����A��ԑ傫���ؑ����͍������哃�ł��B

����R�哃
���̑��A�����n�̂��̂ɂ͐Α��́u�ܗ֓��v��u��⸈v�Ȃ�����܂����A�����ł͏ȗ����܂��B
���̃y�[�W�g�b�v���@�@�����߂����@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
![]()
�Ӑ^3,000�������B
�O�@��t80�������B���������ɁB�s�v�c�Ȃ��Ƃɑ����Ă邻���ł��i������Ƃ����b�͂悭�������j�B
����6���ɐ��g�����C���Ă��āA�Ō�ɎQ�q�҂͓��Ǝ�ɒ����܂��B�s���ׂ��I
�i�Ȃ��A�����͍���������ς��B���N�t�H���ɕ����J����̂ōs���ׂ��I�j
�u�����v�Ƃ�������ɂ́u�����v���������̂ł����A���͑��݂��Ă��܂���B
�ɗ��͔q�߂Α�����B
�܂��A����Ȃ킯�ŁA���E���̎ɗ����W�߂�ƃC���h�ۂقǂɂȂ������ł����A
�C�ɂ����Ⴂ���܂���B
�O�@��t�����̕��ɗ�80���͍b����r�ɕ��[���āA��o���Ɉ��u����A
��X�̒����i�����̃g�b�v�̂��ƁB����R�̃g�b�v�́u����v�Ƃ����B����ɂ���Ă͓������҂�����R��������˂����Ƃ�����j���厖�ɑ厖�Ɏ�삵�Ă����B
�w��⍐�x�Ɂu��������刢苗����A�@�ӕ����쎝���ׂ����N���\�l�v������B
�����ɔ@�ӕ��������@�������Ă���A
�i��������R�ɂ�������A��y����u�ߔN���ۂɍ�������Ƃ�����A�ł��l�͍������Ď肪�o�Ȃ������v
�Ƃ����b�������Ƃ�����B���̃��V�s�ɏ]�������ǂ����͒m��Ȃ����A�u�@�ӕ����č���̂��I�v�Ǝv�����L��������܂��j
����ɂ��ƁA���ɗ�32�����g�p����炵���i���̏ꍇ�A�����ɂ͍ޗ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��悤�����j�B
�܂��u�@�ӕ��͎�X�̕�̒��̍c��ł���A���͎̂߉ޔ@���̕��g�ł���v�Ƃ���B
������
�u��o���̕��ɗ��́A�刢苗����{�炭�`�@��_�����ɂ��ނ悤�ɂ���B
�ꗱ�����ɎU�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����͔@�ӕ��Ȃ̂ł���B
�����i����邱�Ɓj����������邱�ƂȂ̂ł���B
���ɗ��͌��������߂�{�ł����v�Ƃ���B
���ɗ��͕��̎c�[�ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�@���̎�Ȃ�ł��ˁB
�i���Ȃ݂ɁA�E��R�i�x���C�`�T���F�����R�̂��Ɓj�ɂ͑�t�����߁A��X�͖����E��R�Ɍ������Ĕq�ށj
���̓����̕��ɗ��́A�V���L���̎��͑����A���y�����̎��͌������邻���ł��B
�߉q�V�c�̋v����N�l������A����䎺�o�@�e�����������ɗ�����i���H�@�����̂��H�j�A
��������ɔ[�߂ċ����Ɉ��u���A�n�߂Ďɗ�����s���A
�ȗ����`�`�`���Ɩ��N�l��23���ɋ����ő�@������C���Ă��܂��B
���̃y�[�W�g�b�v���@�@�����߂����@![]() �@
�@![]() �@
�@![]()
![]()
�N�ۂT�N�i968�N�j�����̉�^��w���������C�s���N�x�́A���߂āu����v�Ƃ����P�ꂪ�o�Ă���B
���́A���̌�ɑ������ł��B
�������a��N���K�O����\����A�Ђ̍��A�����卿���đ���̒������сA���R�Ƃ��ē��肵���܂��B�i�����j
�R���嫂����l�̔@���A�r�������Ă܂炸�B
���R�Ƃ��Ĉ��u���B
�����A���@�ɏy���Ď��X�̌���ɋy�ԁB
���q���A�����Ȃ���Ȃ��Ĕq�������Ă܂�ɁA��F������颔��X�ɒ����B
�V�Ɉ����Ē䏜�������A�ߏւ𐮂��A�Βd�����ŁA��i�ˁj�ɐl�̏o���肷�ׂ�����Ƃ��B
���̏�ɐΏ��ɋ����ܗւ̗��s�k�����u���A��X�����{�ɗ��������A���̏�ɍX�ɖ������������A�Ŏɗ������u���B
���̎��A����ɐ^�R�m���̉c�ޏ��Ȃ�B
�����ŋC�Â����̂��A���{�ɗ���́u�@�ɗ��v�A���ɗ��͍L�`�̕��ɗ��̓��́u�Ӑg�ɗ��v�ł���u���`�̕��ɗ��v���̂��̂ł��B
�����āA��t�����g�́u�L�`�̕��ɗ��v�̓��́u�S�g�ɗ��v�ł��B
����āA���̓��菊�ɂ́u�ɗ��v�̑S�Ă̗v�f���I�����Ă��܂��B
�ȂA�X�S���ˁH
�����Ă܂��A�����I���i���ɗ���[�߂����j�������I�ܗ֓��������Ă���B
�u�����k�v�Ƃ͓��istUpa�F�X�g�D�[�p�j�̉��ʁi���ʂƂ́A�Ԃ����Ⴏ�u��I����v�n�̓��Ď��ł��j�ł���A
�X�g�D�[�p�Ƃ͂��������ߑ��̈⍜�i�����ɗ��j�����u�������ł������̂��N���ł���Ƃ����̂͐�q���܂����B
�����āA���̓����ܗցi�ܑ�Ƃ������j�A�܂��t�̏������������̐��E�ς��Ȃ��Ă��ĕ\���������̂���{�ł͓��Ɂu�����k�v�Ə̂��܂��B
�X�g�D�[�p�������u���v���Ǝ�ɕ��ɗ������u���铃�₻����N���Ƃ��鍂�������i���╧���ɊW�Ȃ������������u���v�Ə̂��邱�Ƃ�����B�^���[���Ă��Ƃł��ˁj���w�����A
���ʂŁu�����k�v�Ə����Ɩ����̐��E�ς��������₻����N���Ƃ��鋟�{���ȂǂɂȂ�킯�ł��B
�O�q�̒ʂ�A���ɂ́u�ߑ��̈⍜�����u����e��ł���A�ߑ��i�̑����j�̏Z�܂��Ƃł���v�Ƃ�����̗v�f���݂�܂����B
���̓��菊�́A�ɗ������u�����e���ł���A��t�i�Ƃ������g�ɗ��ł��蕧�ł�����j�����ł�����A�Ƃ����������E�E�E�E�E
��t���^�R�R���r�A�ŋ��I�I
���菊�ɂ݂�ɗ��Ɠ��̊W�B
|
�ɗ� |
���ɗ� |
�Ӑg�ɗ� |
�ߑ��̕��ɗ� |
���ɗ��̗e��Ƃ��Ắu���v�B ���p���ł́u�v�A�܂茰���I�ȁu���v�ł���ł����n�����ɋ߂��H �����k�̏�Ɉ��u�����B |
�����I�ȓ� |
�� |
|
�S�g�ɗ� |
��t���g |
�u�b�_���Z�܂��ƂƂ��Ắu���v �ɓ�����A�����I�ȁu���v�B ���p���ł͊�d�Ƃ��čʼn��w�ɂ���H |
||||
|
�@�ɗ� |
|
���{�ɗ��� |
�@�ɗ��̗e��Ƃ��Ắu���v�B ���p���ł́u�����k�v�A�܂薧���I�ȁu���v�B ��d�̏�Ɉ��u�����B |
�����I�Ȍܗ֓��i�����k�j |
�֑��Łu��➈v���Ă̂�����܂����ˁB
�ɗ�������߂Ă������ł��̂ŁA���{�ɗ�������߂��ܗ֓��͕�➈������˂Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B